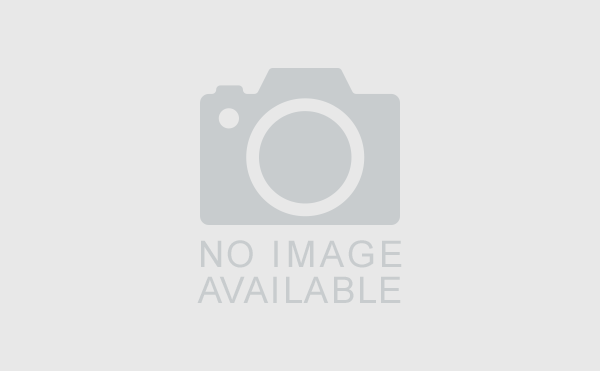【中学理科】体循環と肺循環
Rです。来月から平日毎日バイトをぶち込まれて震えています。
今回は体循環と肺循環について解説します。
先日バイトで中学生から質問され、ややこしいよなあと思いながら教えていたのを思い出し、文字に起こしてみることにしました。
医学部学士編入に挑戦する方々は基本中の基本ですので、全くお役に立たない記事かもしれませんが良ければ見てやってください。
目次
体循環と肺循環
さて、まずは体循環と肺循環について簡単にお話します。
生物は生きていく上で全身に酸素を供給することが必要です。その役割を果たすのが心臓、血管、そして肺です。
①体循環:心臓→全身→心臓という血液の流れ
②肺循環:心臓→肺→心臓という血液の流れ
これだけです。心臓から出た血液が全身に行くのか、肺に行くのかという違いですね。では何がそんなにややこしいのでしょうか?
一つは血液が心臓のどこから何という血管に出て行くのか、またどの血管から心臓のどこに帰ってくるのかを覚えるのが面倒ということです。
心臓は右心房、右心室、左心房、左心室という4つの部屋に分かれています。
そして
右心房:大静脈
右心室:肺動脈
左心房:肺静脈
左心室:大動脈
という感じで繋がっています。これを覚えるのがまず面倒臭い。
動脈と動脈血の違い
なぜこんなややこしいネーミングなのか毎回センスを疑います。体循環と肺循環を考える上で最もややこしいのがここではないかと私は思います。私がこの記事で一番伝えたい所もここです。
ズバリ、「動脈と動脈血は全くの別物」です!
一つずつ説明します。これだけ抑えてもらえれば中学理科は一撃で答えられます。
◎動脈・・・心臓から出て行く血管
◎動脈血・・・酸素を多く含む血管
◎静脈・・・心臓に戻ってくる血管
◎静脈血・・・酸素をあまり含まない血管
これをまず抑えましょう。動脈と動脈血は名前が似ているだけで別物と考えることが重要です。
良く中学生が間違えるのが「動脈=赤」、「静脈=青」という色のイメージです。この覚え方は正しいようで危険です。なぜなら、教科書では動脈ではなく動脈血が赤くなっていることが多いからです。動脈=赤だと思っていると肺静脈がなぜか真っ赤になっていてテンパることになります。
従って、正確な色のイメージは
動脈血=赤
静脈血=青
となります。
そもそも血液が赤く見える理由はヘモグロビンが酸素と結合することによって鮮やかな赤色になるからです。つまり、「酸素を多く含む血液はより赤く見えるし酸素が少ない(二酸化炭素が多い)血液は鮮やかな赤には見えない(青っぽく見える)」というわけです。
○○動脈とか○○静脈というのは人間が覚えやすいよう勝手に名前を付けただけです。色を考えるときに大切なのは血管の名前ではなく酸素の量!これがわかってれば怖い物なしです。
心臓のどこからどの血管が出ている?
生物のテストでは超鉄板の問題です。わかっているようで緊張したテスト本番で出ると意外と焦ります。
しかしここまで読んで動脈、静脈、動脈血、静脈血の違いを理解できた皆さんであればもう一撃で解けます。
例えば心臓の絵が書いてあって心臓→全身に血液を送る血管の名前を答える問題が出たとします。このような問題に答えるためには2つのステップを冷静に踏めば絶対に間違えません。
①心臓から出ている血管なのか心臓に戻ってくる血管かを考える
まずはこれを考えましょう。
a.心臓から出ていく血管=動脈
b.心臓に戻る血管=静脈です。
従って問題の血管は心臓から出ていっている=動脈になります。
後はこの血管が肺動脈なのか大動脈なのかを考えます。つまり「血管がどこと繋がっているのか」を考えればいいわけです。
出ていった血管が肺に向かっていれば肺動脈、全身に繋がりいれば大動脈。これだけです。従って問題の血管は心臓から出て全身に向かっているので大動脈というわけですね。
他の血管もこのステップを踏めば100%正解に辿りつけますので、落ち着いて考えてみてください。
まとめ
今回は体循環と肺循環について書きました。最後にまとめです。
◎体循環と肺循環は心臓から出ていった血液がどこに向かってるかで見極める
◎動脈、静脈、動脈血、静脈血の定義をしっかりと覚える(動脈=動脈血ではない!!)
◎心臓から出て行く血管なのか、心臓に戻ってくる血管なのかを考えれば動脈なのか静脈なのかがわかる。
◎血管が肺、全身のどちらと繋がっているのかを考える。
以上を整理すればこの分野は一撃です。中学生以降の皆さんにとっても知識の整理になれば幸いです。
それでは。